|
|
|
18・19年度の研究部と協力をいただいた先生
|
|
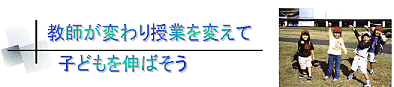
|
|
「英語学習のためのマルチメディア教材開発研究部」
協力
早稲田大学 教授 保崎則雄 先生
「英語学びノート」を活用した効果的な指導法の工夫
|
所沢市では、市内児童・生徒のふるさと所沢を愛する心、実践的コミュニケーション能力の基礎や国際性の育成を目指して、DVD版「英語学びノート」の制作・配布を進めている。昨年度は小学生版を制作し、今年は、その配布と中学生版の制作に取り組んだ。本研究部では、その制作から配布、活用までを視野に入れ、学校現場での児童や生徒の反応を確認しながら、 「英語学びノート」による効果的な指導法の工夫を主題として研究を推進した。
|
|
|
<18年度研究紀要>  1 1 2 2
<19年度研究紀要> 
|
|
<キーワード>
|
○ふるさと所沢を愛する心 ○実践的コミュニケーション能力の基礎
○国際性 ○自ら学ぶ力 ○小学校英語活動 ○小・中学校の連携
|
|
|
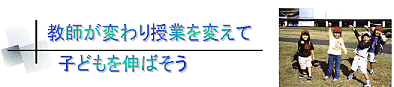
|
|
「特別支援教育に関する専門家チーム委員会の在り方研究部」
協力 立教大学 准教授 大石幸二 先生
東京学芸大学 准教授 藤野 博 先生平成18年度から設置された所沢市特別支援教育専門家チーム委員会は,その内部組織として「教育支援検討班」が編制されていることに特色がある。教育支援検討班は,対象となった園・学校へ指導内容・方法等,具体的教育支援策を提案してきた。また,平成19年度からは,教育支援検討班は巡回相談も担当し,支援対象児の実態把握,評価,指導内容・方法の助言まで連続した支援を行うことができるようになった。本研究は,所沢市特別支援教育専門家チーム委員会における教育支援検討班の役割と成果について,実際に委員会で行われた助言等を整理し,広く資料提供するものである。
|
<18年度研究紀要>  1 1  2 2 3 3
<19年度研究紀要>  1 1  2
2  3
3
|
|
<キーワード>
○特別支援教育 ○特別支援教育専門家チーム ○巡回相談
○教育支援検討班 ○教育支援策
|
|
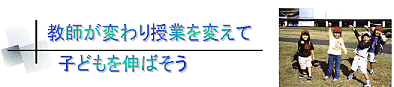
|
|
「教師の資質向上を目指した授業リフレクション研究部」
協力
早稲田大学 教授 浅田 匡 先生
教師の資質向上を目指したよりよい授業リフレクションのあり方
〜リフレクションによる授業改善〜
本研究では、教師の授業力を向上するために、教師が自らの教授行動をふり返り、改善していく授業リフレクションの研究に取り組んだ。
2年次となる本年度は、次の二つの方法を取り上げ、実践を通してその方法を理解し、次年度への課題を明らかにすることに努めた。
○ビデオ視聴をもとにした授業リフレクション
授業を録画したVTRを視聴しながら、事実とその解釈をカードに記述し、KJ法により課題
を焦点化して指導案を改善する方法。
○授業日誌による授業リフレクション
日々の教授活動の中で気になった子どもの姿の記述を積み重ね、対応した手立て等の
個票を行動分類して指導の方策を見出す方法。
|
<18年度研究紀要> 1 1 2 2 3 3
<19年度研究紀要>  |
|
<キーワード>
○授業リフレクション ○授業改善 ○ビデオによる授業のふり返り
○KJ法
○指導案の改善 ○授業日誌法
○個票
○カリキュラムへのフィードバック
|
|
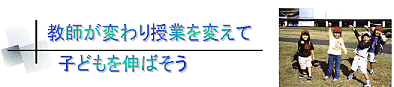
|
|
「情報活用能力の育成を目指した指導法開発研究部」
協力 十文字学園女子大学 准教授 安達一寿 先生
情報活用能力の育成を目指した指導法の開発 ―義務教育9ヵ年を見通した系統性の研究― 「確かな学力」の向上に向けて、基礎基本の徹底や課題解決能力の育成など、学校では様々
な教育活動を展開している。 その中の1つである情報活用能力の育成は、これからの情報化社
会に生きる児童生徒にとって欠くことのできない教育活動である。このことを受け、所沢市では平成1
0年度より、教育ネットワークを構築し積極的に教育活動に取り組んでいる。 しかし、情報教育の実践が進むにつれて各小中学校の実践内容の差が広がり、小学校と中学
校との連携にも支障が出る状況がある。
そこで、所沢市で統一した情報教育のリテラシー表を作成するとともに、その表にそった教
材コンテンツを開発し、合わせて提供することにより、リテラシー表の普及と情報教育の教育
効果を高めることができると考えた。 なお、本年度は、e-L倶楽部というeラーニングソフトウェアにより、授業等でいつでも誰でも利用できる教材コンテンツ の設計と開発にあたっている。 |
|
<18年度研究紀要>  1 1  2 2
<19年度研究紀要>  |
|
<キーワード>
○教材開発 ○e-learning ○情報モラル
○リテラシー段階表(系統表) ○プレゼンテーション
|
|
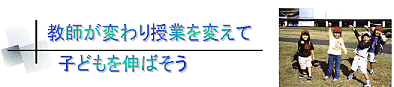
|
|
「個の把握に重点をおいた授業づくり研究部」
協力 千葉大学 准教授 藤川大祐 先生
― 人との関わりを通して個の変容を計る授業づくり −
個々の児童生徒の気づきを蓄積し、その中から変容させたい児童生徒(位置づけた児童生徒)を抽出する。
位置づけた児童生徒と周りとの関わりを通して、変容させることをテーマに授業づくりを進めた。また、その児童生徒が他と関わることで、周りの学びの姿がより見えてくることをねらった。 |
|
<18年度研究紀要>  1 1 2 2
<19年度研究紀要>  |
|
<キーワード>
○個 ○関わり ○気づき ○位置づけた児童生徒
○白紙座席表 ○授業メモ ○場づくり(リソース)
○ストップモーション方式による授業記録 |
|
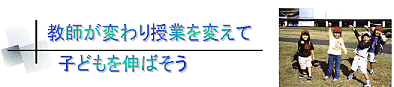
|
|
「図画工作科、美術科の学力保障カリキュラム開発研究部」
協力 文教大学 准教授 三沢一実 先生 ―文教大学との共同研究―
図画工作科・美術科の基礎基本とは何か。その題材で子ども達につけたい力、
つけるべき力とは何か。
こうしたものを教師が持っていなければ、子ども達に学力を保障することができない。そこで私たちは所沢市内の教職員、市民を対象に図画工作科・美術科に対する意識調査を行い、分析し、課題をより明確化した。
昨年度は小学校、図画工作科における基本カリキュラムを提案した。今年度は意識調査の更なる分析と中学校、美術科における各内容を通して、共通してつけたい力を明示し、各題材ごとに提案していく。 |
|
<18年度研究紀要> 1 1  2 2
<19年度研究紀要>  |
|
<キーワード> ○基礎・基本 ○学力保障 ○つけたい力 ○意識調査 ○学習指導要領 ○カリキュラム ○美術科 ○図画工作科 |