
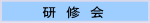 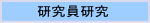 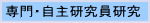 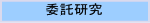 |
|
|
| 令和3年度の研究 |
|
|
【統合版】 所沢市立教育センター研究紀要 |
|
|
Ⅰ 授業実践 ~主体的・対話的で深い学びを実現するために活用するICT |
|
|
1 国語科研究部 「充実した言語活動の中で、自信を持って話し合いに臨む児童・生徒の育成」 |
|
|
2 社会科研究部 「新学習指導要領における『思考力・判断力・表現力』の評価の研究」 |
|
|
3 理科研究部 「主体的・対話的で深い学びの視点からの指導の工夫 ~ICTえお活用して~」 |
|
|
4 外国語活動・外国語科研究部 「児童・生徒が主体的に学ぶ導入の工夫について」 |
|
|
Ⅱ 事務研究 |
|
|
1 学校事務研究部 「Googleアプリケーションを活用した学校運営の効率化・学校関係諸費の会計一本化」 |
|
|
令和元年度の研究 |
|
|
【統合版】 研究員研究紀要 |
|
|
授業実践 ~主体的・対話的で深い学びの視点からの指導の工夫~ |
|
|
Ⅰ 算数・数学科研究部 「問題発見・解決の過程の遂行を通して」 |
|
|
Ⅱ 図画工作科研究部 「『つくる喜び』 『広がる想い』 『豊かな表現』」 |
|
|
Ⅲ 道徳科研究部 「伝え合いを通して自己の生き方についての考えを深める授業の展開」 |
|
|
教育相談研究 |
|
|
Ⅳ 教育相談研究部 「児童生徒の適応力を高める手立てと体制づくり」 |
|
|
平成30年度の研究 |
|
|
授業実践 ~主体的・対話的で深い学びの視点からの指導の工夫~ |
|
|
Ⅰ 国語科研究部 「言葉による見方・考え方を働かせるための言語活動の研究」 |
|
|
Ⅱ 社会科研究部 「社会的な見方・考え方を働かせるための課題設定や問いの追究」 |
|
|
Ⅲ 理科研究部 「ものづくりを通した深い学びの実現」 |
|
|
Ⅳ 外国語活動・外国語科研究部 「英語絵本を活用した指導の研究」 |
|
|
Ⅴ 特別活動研究部 「豊かな関わり合いを通して、自発的・自治的な活動のできる児童生徒の育成」 |
|
|
事務研究 |
|
|
Ⅵ 学校事務研究部 「子どもたちのためにできること」 |
|
|
平成29年度の研究 |
|
|
授業実践 |
|
|
Ⅰ 算数・数学科研究部 「数学的な思考力・表現力の向上を目指した主体的・対話的で深い学びの探求」d |
|
|
Ⅱ 図画工作科研究部 「主体的に表現する児童の育成~ともに学び合い高め合う活動~」 |
|
| |
Ⅲ 小・中学校道徳研究部 「一人一人の思いを素直に表現できる児童生徒の育成」 |
|
| |
教育相談研究 |
|
| |
Ⅳ 教育相談研究部 「すべての児童生徒への教育相談的手法の研究」 |
|
| |
事務研究 |
|
| |
Ⅴ 学校事務研究部 「事務の円滑化による校務改善―今できるグループワーク所沢プラン―」 |
|
| |
平成28年度の研究 |
|
| |
授業実践 |
|
| |
Ⅰ 小・中学校国語研究部 「生き生きと自ら学ぶ児童生徒の育成―自分の考えをもち、伝え合うことのできる授業の研究―」 |
|
| |
Ⅱ 小・中学校社会研究部 「主体的・協働的な学びを通して、多様な考えを引き出す授業―社会科好きを育てるための魅力的な問いを求めて―」 |
|
| |
Ⅲ 小・中学校理科研究部 「言語活動を取り入れることによる学習効果―メタ認知に関わる能力の獲得と言語活動の関わりについて―」 |
|
| |
Ⅳ 外国語活動・外国語研究 「4技能への積極的な態度の育成と学びの連続性を図る授業の工夫改善」 |
|
| |
Ⅴ 小・中学校特別活動研究部 「主体的・協働的な学びの探究―互いのよさを認め合い、話合い活動を充実させるための工夫―」 |
|
| |
教育相談研究 |
|
| |
Ⅵ 不登校予防研究部 「共感的な人間関係のなかで、一人一人の自己存在感をはぐくむ授業づくり―みんなの”いいトコろん”集め―」 |
|
| |
事務研究 |
|
| |
Ⅶ 学校事務研究部 「事務の円滑化による校務改善―グループワーク所沢プランの可能性―」 |
|
| |
平成27年度の研究 |
|
| |
授業実践 |
|
|
Ⅰ 小・中学校国語研究部「読む力を確かなものにするための交流場面における指導の工夫」 |
|
|
Ⅱ 算数・数学研究部 「児童生徒の思考力・表現力の育成 -学びあいの視点を取り入れた算数・数学的活動の充実-」 |
|
|
Ⅲ 小・中学校理科研究部 「思考力•表現力を育成するための授業実践 -アクティブ•ラーニングを取り入れた実践•提案-」 |
|
| |
Ⅳ 外国語活動・外国語研究 「交流の活性化を図るコミュニケーション活動の工夫」 |
|
| |
Ⅴ 小・中学校音楽研究部 「音楽表現を高めるための言語活動の充実」 |
|
| |
Ⅵ 図画工作研究部 「対話を通して、自分の思いを表現する図画工作科の指導の工夫」 |
|
| |
Ⅶ 小・中学校道徳研究部 「ねらいに迫る 道徳の授業の工夫 -教科化に向けた道徳の時間の充実を目指して-」 |
|
| |
Ⅷ 小学校特別活動研究部 「望ましい集団活動を通した言語活動の充実―教師の支援をもとにして主体性を育み認め合える学級作り―」 |
|
| |
教育相談研究 |
|
| |
Ⅸ 不登校予防研究部 「市内小・中学校の不登校ゼロを目指して―教室で育てよう!楽しさの木―」 |
|
| |
Ⅹ 小・中学校特別支援教育研究部 「通常学級の中で理解を促す合理的配慮の研究」 |
|
| |
事務研究 |
|
| |
Ⅺ 学校事務研究部 「事務の円滑化による校務改善 ―適正在庫量に基づいた予算執行―」 |
|
| |
平成26年度の研究 |
|
| |
教育実践 |
|
| |
Ⅰ 小・中学校国語研究部 |
|
| |
「聴き合い・学び合い・深め合い」 ~物語文を中心とした「読むこと」における指導の工夫~ |
|
| |
Ⅱ 算数・数学研究部 |
|
| |
「児童生徒の思考力・表現力の育成」 ~説明する活動の充実を通して~ |
|
| |
Ⅲ 小・中学校理科研究部 |
|
| |
「思考力・判断力・表現力を育成するための言語活動の充実」 |
|
| |
Ⅳ 外国語活動・外国語研究 |
|
| |
「小学校におけるコミュニケーション能力の素地の育成と中学校への接続」~小学校で実践している活動を中学校へどのようにつなげていけばよいか~ |
|
|
Ⅴ 小・中学校音楽研究部 |
|
| |
「音楽科の学習の質を高めるための言語活動の充実」
~共通事項を共有・活用し、創造的に音楽と関わる児童・生徒の育成~ |
|
| |
Ⅵ 小・中学校道徳研究部 |
|
|
「自己肯定感を高め、自分の思いをのびのびと表現できる道徳の時間の指導」 |
|
| |
Ⅶ 小学校特別活動研究部 |
|
| |
「学級における望ましい集団のあり方」 ~意欲的な活動を育てるための教師の助言と評価~ |
|
| |
Ⅷ 小・中学校特別支援教育研究部 |
|
| |
「合理的配慮の視点に立った教科指導」 |
|
| |
教育研究 |
|
| |
Ⅸ 不登校予防研究部 |
|
| |
「市内小・中学校の不登校ゼロを目指して」 ~不登校予防のための学級でできるこころの土台づくり~ |
|
| |
事務・食育研究 |
|
| |
Ⅹ 学校事務研究部 |
|
| |
「地域に開かれた安全・安心な学校づくり」 ~事務職員が考える学校防災~ |
|
| |
ⅩⅠ 食育研究部 |
|
| |
「誰にでもできる楽しい食育」 ~給食時間の充実~ |
|
|
平成25年度の研究 |
|
| |
Ⅰ 小・中学校国語研究部 |
|
| |
「思考力・判断力・表現力の育成を図る指導法の工夫と検証」
~トゥールミンモデルを利用した意見文を書くことを通して~ |
|
| |
Ⅱ 小・中学校社会研究部 |
|
| |
「児童・生徒が主体的に学び、思考力・判断力・表現力を伸ばす社会科学習指導」
~小・中を見通した判定基準を踏まえた課題解決評価の工夫~ |
|
| |
Ⅲ 算数・数学研究部 |
|
| |
「数学的な思考力・表現力を育てる評価」 ~小・中の接続を意図した能力形成と支援方法による効果の検証~ |
|
| |
Ⅳ 小・中学校理科研究部 |
|
| |
「単元一貫課題を用いた思考力・判断力・表現力の育成」 |
|
| |
Ⅴ 外国語活動・外国語研究 |
|
| |
「思考力・判断力・表現力の向上を目指した支援の手立てとその検証」 |
|
| |
Ⅵ 小・中学校音楽研究部 |
|
| |
「音楽教育における形成的評価の在り方」~形成的評価を利用した鑑賞・器楽・歌唱の授業内容と指導法~ |
|
| |
Ⅶ 小学校特別活動研究部 |
|
| |
「学級活動(1)における児童の思考力の育成を図る指導法の工夫」~教師のよりよい指導助言と評価について~ |
|
| |
Ⅷ 小・中学校特別支援教育研究部 |
|
| |
「特別支援教育の視点に立った、だれもが学びやすい教室づくり」 |
|
|
教育研究 |
|
| |
Ⅸ 不登校予防研究部 |
|
| |
「市内小中学校の不登校ゼロを目指して」 ~小・中教員の実践アンケートに基づいた不登校未然防止の対策~ |
|
|
事務・食育研究 |
|
| |
Ⅹ 学校事務研究部 |
|
| |
「事務の円滑化による校務改善」 ~共通化・共有化による校務改善~ |
|
| |
ⅩⅠ 食育研究部 |
|
| |
「誰でもできる楽しい食育」 ~給食の時間の充実と、意欲を喚起する授業の工夫~ |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Ⅲ 小学校理科研究部 |
|
|
「児童の思考を発揮させる指導法の研究」 |
|
|
Ⅳ 小学校外国語活動研究部 |
|
|
「積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成を目指して」 |
|
|
Ⅴ 中学校社会研究部 |
|
|
「生徒が主体的に学び、思考力・判断力・表現力を伸ばす社会科学習指導」 |
|
|
Ⅵ 中学校数学研究部 |
|
|
「思考力・表現力を伸ばす学び合いの授業」 |
|
|
Ⅶ 中学校理科研究部 |
|
|
「科学的思考力・表現力を高める授業の研究」 |
|
|
Ⅷ 中学校外国語研究部 |
|
|
「『聞くこと』『話すこと』『読むこと』『書くこと』の4技能を総合的に活用できる生徒の育成」 |
|
|
Ⅸ 道徳教育研究部 |
|
|
「『生きる力』と『伝え合う心』をはぐくむ道徳教育をめざして」 |
|
|
教育研究 |
|
|
Ⅹ 不登校予防研究部 |
|
|
「市内小中学校の不登校ゼロを目指す」 |
|
|
ⅩⅠ 情報活用能力育成法開発研究部 |
|
|
「情報機器を活用した情報活用実践力の育成を目指した指導方法の開発」 |
|
|
事務・食育研究 |
|
|
ⅩⅡ 学校事務研究部 |
|
|
「事務の円滑化による校務改善」 |
|
|
ⅩⅢ 食育研究部 |
|
|
「誰にでもできる食育」 |
|
|
| 平成22年度の研究 |
|
|
教育実践 |
|
|
Ⅰ 小学校国語研究部 |
|
|
「思考力・判断力・表現力を育成する指導法の工夫 -説明し、書く活動を通して-」 |
|
|
Ⅱ 小学校算数研究部 |
|
|
「数学的な思考力・表現力の育成」 |
|
|
Ⅲ 小学校理科研究部 |
|
|
「児童の学び方を高める指導法の研究 ~『学び方アイテム』を活用し、指導法の開発に取り組むことを通して~」 |
|
|
Ⅳ 小学校外国語活動研究部 |
|
|
「『英語学びノートDVD』を活用した小学校外国語活動の授業提案」 |
|
|
Ⅴ 中学校国語研究部 |
|
|
「学び合いを通して思考力、判断力、表現力の育成を図る授業の研究(言語事項教材を使って)」 |
|
|
Ⅵ 中学校社会研究部 |
|
|
「社会的事象を多面的・多角的に考察し、主体的に社会に関わる性との育成」
-社会的な見方・考え方を育てる授業づくりについて- |
|
|
Ⅶ 中学校数学研究部 |
|
|
「思考力・判断力・表現力を育成する発問の工夫」 |
|
|
Ⅷ 中学校理科研究部 |
|
|
「科学的思考力を高める授業の創造 ~図やモデルを基に説明する力の育成~」 |
|
|
Ⅸ 中学校外国語研究部 |
|
|
「新学習指導要領をふまえた指導法の改善 -思考力・判断力・表現力の育成を目指して-」 |
|
|
Ⅹ 道徳教育研究部 |
|
|
「道徳の授業を充実する資料分析と発問の工夫 ~多様な形式の指導方法の工夫~ 」 |
|
|
教育研究 |
|
|
ⅩⅠ 不登校予防研究部 |
|
|
「市内小中学校の不登校ゼロを目指して ~校内組織でのマッピングを活かした個別支援計画の作成~」 |
|
|
ⅩⅡ 情報活用能力育成法開発研究部 |
|
|
「情報機器を活用した情報活用実践力の育成を目指した指導方法の開発」 |
|
|
学校事務研究 |
|
|
ⅩⅢ 学校事務研究部 |
|
|
「事務の円滑化による校務改善 ~データの共通化、共有化による校務改善~」 |
|
|
平成21年度の研究 |
|
|
教育研究 |
|
|
Ⅰ 小学校外国語活動教育研究部 |
|
|
「『英語学びノート』を活用した小学校外国語活動授業の提案について」 |
|
|
Ⅱ 不登校児童生徒への対応研究部 |
|
|
「市内小中学校の児童生徒不登校ゼロを目指した校内支援体制及び未然防止の取組について」 |
|
|
Ⅲ 情報活用能力の育成法開発研究部 |
|
|
「情報活用能力の育成を目指した指導法の開発」 |
|
|
Ⅳ 知識・技能を活用する学習活動研究部 |
|
|
「思考力を育成する『考えるための技能』の活用」 |
|
|
Ⅴ 総合的な学習の時間授業開発研究部 |
|
|
「総合的な学習を成立させるための諸要件の研究」
~ 総合的な学習の時間の中で、特に「探求的学習成立」に視点をあてて ~ |
|
|
教育実践 |
|
|
Ⅵ 小学校算数研究部 |
|
|
「見通しをもち、筋道を立てて考え、表現し説明する能力の育成を目指して」 |
|
|
Ⅶ 小学校・中学校理科研究部 |
|
|
「科学的な思考力を育成する理科指導の工夫について」 |
|
|
Ⅷ 中学校国語言語活動研究部 |
|
|
「思いが共有できる発表の場をめざして」 |
|
|
Ⅸ 中学校数学研究部 |
|
|
「一人ひとりの思考力・表現力をのばす学びあいの授業をめざして」 |
|
|
Ⅹ 中学校総合的な学習の時間研究部 |
|
|
「探求的な学習を通した総合的な学習の時間の授業づくり」 |
|
|
Ⅺ 道徳教育研究部 |
|
|
「自己の生き方・人間としての生き方を深める道徳教育」 |
|
|
|
|
|
平成20年度の研究 |
|
|
Ⅰ 小学校外国語活動中学校英語教育研究部 |
|
|
「中学校英語へのスムーズに接続する小学校外国語活動の在り方について」 |
|
|
Ⅱ 不登校児童生徒への対応研究部 |
|
|
「市内小中学校の児童生徒不登校ゼロを目指した校内支援体制及び未然防止の取組について」 |
|
|
Ⅲ 教師の資質向上を目指した教育メンター研究部 |
|
|
「教師の資質向上を目指したメンタリングの在り方について」 |
|
|
Ⅳ 情報活用能力の育成法開発研究部 |
|
|
「情報活用能力の育成を目指した指導法の開発」 |
|
|
Ⅴ 知識・技能を活用する学習活動研究部 |
|
|
「活用力を高め、より良く生きようとする児童の育成」 |
|
|
Ⅵ 地域の実態を生かした総合的な学習の時間授業開発研究部 |
|
|
「横断的・総合的な学習、探究的な学習を大切にする総合的な学習の時間の研究」
~ 総合的な学習の時間を成立させる用件の提案 ~ |
|
|
|
|
|
平成18・19年度の研究 |
|
|
Ⅰ 英語学習のためのマルチメディア教材開発研究部 |
|
|
「英語学びノート」を活用した効果的な指導の工夫 |
|
|
Ⅱ 特別支援教育に関する専門家チーム委員会の在り方研究部 |
|
|
Ⅲ 教師の資質向上を目指した授業リフレクション研究部 |
|
|
教師の資質向上を目指したよりよい授業リフレクションのあり方 ~リフレクションによる授業改善~ |
|
|
Ⅳ 情報活用能力の育成を目指した指導法開発研究部 |
|
|
情報活用能力の育成を目指した指導法の開発 ―義務教育9ヵ年を見通した系統性の研究― |
|
|
Ⅴ 個の把握に重点をおいた授業づくり研究部 |
|
|
人との関わりを通して個の変容を計る授業づくり |
|
|
Ⅵ 図画工作科、美術科の学力保障カリキュラム開発研究部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(c) 2009 Tokorozawa Education Center All Rights Reserved |
|